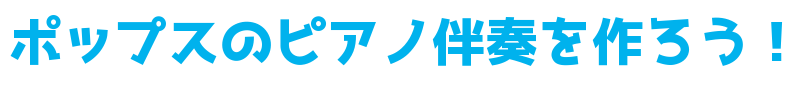5-3.隣のコードを使ってみよう

3つずらす、っていうのは隣のコードを使えるってことだよね?

実はあまりピアノ伴奏には実用的じゃないピけど、一瞬ならそういうことができるピ。
3つの音をずらす
Cの代わりにCsus4を使う場合は、音を1つずらしていることになります。Cの代わりにFを使う場合は、音を2つずらしていることになります。
いずれにしろ、共通音が残っていることで、コードの響きを保っているのですが、3つの音をずらすと完全に違うコードとなります。
たとえば、隣のコードは3つの音がすべて異なるコードとなります。
Cに対して、Bとか、Dmとか、D♭とかです。実際の使い方を見てみましょう。
伴奏に隣のコードを使ってみよう!
( )の中が、ここでいう「隣のコード」のことです。基本のコード進行「C→F→Fm」に、色々なコードを混ぜています。Cに対してのBやDmには、共通音が一つもありませんが、Cの響きを保ったまま進行していることがわかると思います。
「アリ」なコードと、「ナシ」なコード
隣のコードと一口に言っても、その構成音によって楽曲に溶け込むコードと、溶け込まないコードがあります。
上記の動画では、ナシなコードはCに対してのBです。完全に調性外の音を使っています。この場合、一瞬であれば使っていいのですが、すぐにもとに戻すべきです。
逆に、Cに対してのDmはアリなコードです。隣にずれてはいるものの、調性内の音を使っているため、違和感はありません。また、Dmはサブドミナントとして機能しているので、Fと似た響きを持っています(Cに対してFを使っていい、ということは前回学習しましたね)。
同様に、Fに対してのGも、調性内の音なのでOKです。Fmの部分は少しむずかしいことをしてしまいましたが、ここだけCmの調性になっていると考えれば、これも調性内の音を使った隣のコードです(試しに、FmのところでGを弾くと濁って聞こえるかと思います)。
広瀬香美「ゲレンデがとけるほど恋したい」の前奏でも、隣のコードから目的のコードに向かって上昇するフレーズを使用しています。
特に、半音ですべてのコードを移動させるのは、ピアノではあまり見かけませんが、ギターの伴奏ではよく使われるパターンです。
この章のまとめ
CHECK
- 3つの音をずらして、隣のコードを使ってみよう
- 隣のコードを使ったらすぐにもとに戻すか、次のコードにつなげよう
- 調にない音を使った場合は、特にすぐに戻そう